お早うございます。
今週は宇都宮事務所からのスタートです。
先週末は土日とも晴天となり、気温もグングン上昇、初夏の陽気となりました。
好天が続く中、土曜の午前中は事務所にて雑務をこなした後、どうしても土曜日でないと面談できない取引先にお邪魔した後、午後からは「趣味」と云うか「お遊び」の時間を過ごしました。
田舎暮らしの特権ですが、実家には自家の雑木林があり、そこからコナラの木を自宅に持ち帰り(土曜日)、昨日
日曜日にシイタケの種駒をホームセンターに求め、午後、植菌作業をしていたのです。
文章にしてしまうと、簡単なんですが、これがなかなかの重労働で…
今どき、実家付近のド田舎でも「山から木を伐(き)って来てキノコ菌を植菌して栽培しようとする人」なんて一人も居ません(笑)
でも浦和に引っ越して来た次男嫁&孫娘がキノコ類好き、特にナメコが大好きらしく「それなら爺ちゃんが山に行って木を伐ってナメコを育ててみるわ」と約束したのがキッカケでして…
メインのナメコ菌は二週間前にブナ・イタヤカエデを伐り出して植菌済ですが、気温が上がると植菌作業もできなくなる(雑菌繁殖とのバランスでしょうか)ので、ついでにシイタケもやっちゃおうとのノリでしたが。
私のやろうとしていたのは、いわゆる「原木栽培」と言われるキノコの栽培方法で、晩秋~初春にキノコ菌を植える原木を山から伐りだし、原木に植菌用の穴を開け(電動ドリルを使います)市販のキノコ菌を入手、原木の穴に打ち込んだ(金づちを使います)後、数週間養生の後で自然に近い環境(裏山等の風通しの良い日陰)に設置、後はひたすら待つだけの栽培方法です。
だいたい二年くらいすると、原木からキノコが“にょきにょき”出て来ます。
キノコ栽培にも「適木(てきぼく)」という概念があって、例えばナメコはサクラ・ブナが最適木ですし、シイタケはコナラ・クヌギが最適木と言われています。
入手できる原木の種類によって栽培できるキノコの種類が変わって来るので、キノコの選択もそうですが、適木の選定とかにも頭を使うんです。
今年は、他にブナ・カエデを適木とするヒラタケも植菌したので、二年後が楽しみです。
孫娘が収穫する事の愉しみを知って「私もやりたい!!」とか言ってくれるようなら、また二年後も「山に柴刈りに」行く事になるかも知れません。
年々年をとるので原木の重さに耐えられるか??ですが、カワイイ孫のためなら頑張れそうな気がします(笑)



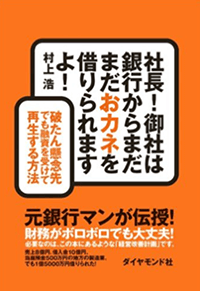
コメント
※コメントは承認制となっております。承認されるまで表示されませんのでご了承ください。