新潟県を地盤とする第四北越FG(フィナンシャルグループ)と群馬県に本店を置く群馬銀行が、2年後の経営統合を目指して調整中である事が報道されました。
両行…、いや第四北越は第四銀行と北越銀行で構成されているので、群馬銀行を合わせると3行になりますが、総資産は21兆円を超え、地銀カテゴリーでは福岡FG、横浜銀行を中核とするコンコルディアGに次ぐ規模となり、千葉銀行や常陽・足利を傘下に持つめぶきFGをも凌ぐ地銀グループとなるようです。
地銀では、静岡銀行・八十二銀行・山梨中央銀行の三行による経営統合も噂されていて、営業基盤が隣県通しの第一地銀クラスの合従連衡がこの後も進みそうです。
もはや各県に一行ずつあった「一国一城」的な地位は崩れ去り、規模が大きいメガバンクや小規模ながらきめ細かいサービスに特化する信金・信組に対抗するには、ある程度の経営規模と効率化を目指さるを得ない地銀の苦境が伺い知れるようにも見えます。
地銀を巡っては、海外の債権投資に関連した「含み損」処理の問題もあります。
これは大手地銀より、規模の小さい第二地銀以下の業態の金融機関が抱えている問題だと思いますが、保有する資金を海外の高金利債権を購入する事で運用する中、債券価格が予想以上の騰落を見せる時、顕在化する問題です。
運用先(融資先)の乏しい首都圏から離れた地域を地盤とする銀行などが、過去に何度も経験している問題ですが、不思議と20年くらいの時間軸の中で必ずと言っていいほど「数百億円、一千億円単位での損失処理」等の報道がされます。
先日のトランプ関税砲では世界中の株式相場が乱高下しましたが、同時にアメリカ国債も暴落したようです。
こういう時に「安全且つ高利回り」を信じて購入した債権が突然暴落したり、邦銀が保有する債権の一部にでも米国債や株式が運用先に含まれていると、思わぬ火傷を負う事もあるのです。
昨年は二回も「短期プライムレート」を引き上げる事ができ、収益が上ブレ始めた地銀カテゴリーですが、単独で生き残っては行けないとの共通認識が、業界内には浸透して来ています。
第四北越・群馬銀行に続く経営統合案件も、今後どんどん日の目を見て行く事でしょう。
経営体力が向上するなら、各種サービスの手数料等も見直して貰いたいものです。
地域内のシェアがより高まって「競争原理」が働かなくなるようなら、利用者としては、経営統合なんてして欲しくなくなりますよね(笑)



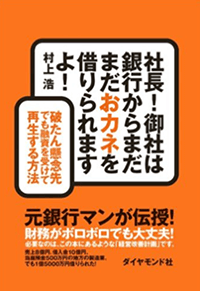
コメント
※コメントは承認制となっております。承認されるまで表示されませんのでご了承ください。